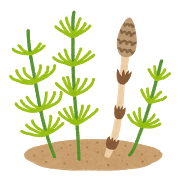バルトのいた頃
榊原(はっぱ)です。
ずっとずっと前の夏。
主人が子犬を連れて会社から帰ってきた。
見た時に熊のぬいぐるみかと思ったほど、茶色のふさふさの毛でまるまる太っていてかわいかった。
子どもたちは大喜びだったが、私は動物が好きではなかったし、犬や猫を飼ったことがなかったから、
飼うことに反対した。
「飼うには責任がいるんだよ。誰が世話をするの?!返してきて!!」と主人を責めた。
その子犬は本当にかわいくて、頭もよく、おしっこの粗相も一度もなかった。
「おいで」と呼ぶと全速力で駆けてくる、そのかわいらしい姿に、私はきゅんとなった。
数日後の返しに行くと決めた日、私は涙が止まらなかった。
かわいくて、かわいくて、かわいすぎたからだ。
隣(完全分離の二世帯住宅)に住んでいる父母が
「協力するから飼おうよ。」と言ってくれて、
子犬は家族となった。
恋をするとはこんな気持ちなのだろうか。
私は仕事をしている時も子犬のことを思い出してはきゅんとなった。
やんちゃをして母に叱られてプランターの中にすっぽり入って反省している姿がかわいかった。
名前は息子がつけた。
ペニシリンを運んだオオカミ犬の話を図書館で読んだらしく、
その犬の名前が「バルト」というので、そうつけた。
バルトは頭のいい犬だった。
「待て」「お手」「お座り」「ふせ」もすぐ覚えた。
「待て」と言われれば「よし」と言うまでずっと待った。
ある時、母が食べ物を前に置き「待て」と命令をして、
他の用事をしていてすっかり忘れていると、
バルトはよだれをたらりたらりとたらして待っていたそうだ。
驚くのは命令した人をよく覚えていることだ。
例えば、私が餌を前にして「待て」と命令したら、
母が「よし」と言っても絶対に食べない。
母が「待て」と言ったら私が「よし」と言っても食べないのだ。
頭がいいだけでなく、気持ちも優しい犬で、
私が悲しくて涙を流すと近づいて涙をなめてくれた。
夫婦喧嘩をすると、強い方をワンワンと叱って仲裁に入ってくれた。
子どもを叱ると、叱っている私にワンワンと吠えた。
私たちが通ろうと思っているところにバルトが寝ていると、
そっと道を譲ってくれたりもした。
無駄吠えはなかったが、家族以外の人が一歩でも敷地に足を入れたらワンワンと吠えた。
いい番犬だった。
バルトにとって「一番の仲良し」は父で、息子のことは「お兄ちゃん」と思っていて、
娘は「妹」と思っていたようだ。
母は「恐いご主人様」で、主人は「気のいいおっちゃん」だ。
私のことは何だと思っていたのだろう。
バルトは外で飼っていたので、家に上がってくるということは絶対になかった。
しかし、バルトの毛はふさふさで、たぶん寒い地方で飼われていた犬の血が流れていると思われるので、
夏に弱い。
クーラーの効いた玄関に入れてやろうと思うのだが、
バルトは遠慮してなかなか入ってこない。
毎年夏は、申し訳なさそうに玄関で過ごしていた。
そんなバルトに父は犬用の扇風機を買ってきたり、いろいろ涼しくなる工夫をしていた。
父が毎日バルトを散歩に連れていった。
バルトがかわいくてしかたがなかったのだろうと思う。
バルトも父が大好きだった。
バルトもだんだん年をとり、家に人が入ってきても吠えなくなった。
それでも、父との散歩は毎日行っていた。
ある日、散歩の途中でバルトはバタンと倒れた。
少し前から息苦しそうで元気がなかったが、
大好きな父との散歩は極限になるまで頑張って行っていたのだろう。
バルトの逝った日は、主人が脳梗塞で何か月も入院していて外泊許可をもらい家にいた日だった。
息子も次の日、金沢から帰ってくることになっていた。
バルトはその日、やはり玄関で苦しそうにしていた。
私はずっとそばにいた。
バルトは苦しそうにしているのに、何度も外に出ていこうという素振りをする。
よたよたで玄関の扉に向かって立ち上がる。
家の中にいて申し訳ないという気持ちなのか。
いいよ。いいよ。お家の中にいていいよ。
こんな時まで気をつかわなくていいよ。
夜中、父と母を呼んだ。
父は見たくないのか、すぐどこかに行ってしまった。
私は苦しむバルトを抱いて言った。
「バルト、お兄ちゃんを待っているのかもしれないけど、もういいよ。
明日、お兄ちゃんにはバルトのこと伝えておくから、
バルト、もう楽になってもいいよ。」
そう言うと、バルトの体から魂がぬけてくのを感じた。
バルト、ありがとね。
いっぱい、いっぱい、ありがとね。
あれから3年半。
今頃は天国で走り回っているだろうなと思えるようになったので、
テーブルの上のバルトの写真は大事に引き出しにしまった。
バルト、我が家に来てくれてありがとう。
今年も夏が来た。
バルトがやってきて夏が来た。